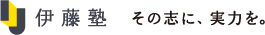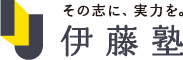第17号 難民の数から考えること
有馬 みき(東京大学 難民移民ドキュメンテーションセンター 特任研究員)
6 月 20 日は「世界難民の日」でしたが、この日に合わせて国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)が 2012 年の統計を発表しました。それによると昨年(2012 年)1 年間で、新たに 110 万人が難民となりました。
平均すると毎日約3千人の人々が難民となった計算になります。
シリア、コンゴ、マリ、スーダン等における紛争が難民の大量流出の主な原因です。
これに加えて、世界で 90 万件近くの個別の難民認定申請が行われました。
日本の場合はどうでしょうか。2012 年に日本で難民認定申請を行った人は 2545 人、そのうち難民だと認定された人は 18 人(うち異議申立手続における認定者 13 人)、また第三国定住により受け入れられた難民はゼロでした。
申請数は日本にとっては過去最高で、このような申請数の増加に対して危機感を抱く人もいます。
しかし、前述の世界の数字に照らすと、日本における難民認定申請者や日本にいる難民の数が、いかに少ないかがお分かりいただけると思います。
裁判に関しても同様です。個別の難民申請を多く受理している先進諸国では難民認定に関する訴訟も多いため、難民法を専門にする弁護士や裁判官が大勢います。
世界各国の裁判官や難民認定担当者から構成される国際難民法裁判官会議(IARLJ) というネットワークがありますが、そこに参加している日本の裁判官は一人もいません。
日本にも難民不認定処分を争う行政訴訟はあるものの、難民法を専門にする裁判官がいないのです。
とはいえ、行政訴訟のうち約3割は出入国管理及び難民認定法に関する事件です。
数は少なくても、難民一人ひとりが抱える悩みは決して小さなものではありません。
日本に逃れて来て、言葉もよく分からないなか、難民認定申請を行わなければならない人たちにとって、自分の主張を代弁してくれる弁護士の存在はとても大きなものです。
今後、このコラムを読んで下さっているみなさんの中からも、この分野を専門とする法律家が増えていくことを期待しています。
アメリカでは、昨年1年間だけで7万件以上の難民認定申請を受理し、66,300 人の難民を第三国定住制度により受け入れました。
日本に比べると、もともと移民国家であるという素地の違いはありますが、これだけの数を受け入れていれば、普通にアメリカに暮らしている人が難民と接する機会もおのずから増えるものです。
身近なところに難民や難民認定申請中の人がいれば自然と関心を抱き、理解が深まります。
友人、隣人、あるいは同僚に難民がいれば、難民を単なる社会の重荷だと考えることはないでしょう。
一方、日本の場合は、そもそも難民に出会う機会が少ないために、難民問題への理解を深めるきっかけが少ないともいえます。
もっとも、難民の数が多くなると国民の一部の反感を招くこともあり、国によっては対応の是非が政治を左右することさえあります。
日本国内で難民問題が議論されることは決して多いとはいえませんが、私が UNHCR駐日事務所で働きはじめた 15 年ほど前に比べれば、確実に裾野が広がっていると感じています。
まず、メディアで難民に関する報道を目にすることが増えました。
最近では日本国内の難民について、分かりやすく紹介する書籍が何冊か出版されています。
たとえば、『日本と出会った難民たち』(根本かおる著、英治出版、2013 年)や『海を渡った故郷の味』(認定 NPO 法人難民支援協会、ジュリアン、2013 年)などです。
これらの中でも紹介されているように、難民と出会う日本人は増えてきているのです。
また学問の分野においても、これまでは難民研究というと法律や国際政治の分野に偏りがちでしたが、今日ではソーシャルワークや精神医学等、幅広い分野で 研究が行われるようになり、「難民研究ジャーナル」(難民研究フォーラム編集)や「CDR Quarterly」(東京大学 CDR 編集)といった、日本生まれの難民研究誌も誕生しました。
このような状況のなか、日本国内の難民支援 NGO のネットワーク組織である「なんみんフォーラム」は、難民保護法の制定に向けた提言を発表しました。
次回からは、この提言内容についても紹介しながら、日本の難民をめぐる課題について考えていきたいと思います。
伊藤塾塾便り215号/HUMAN SECURITYニュース(第17号 2013年7月発行)より掲載